小樽商大
2016年10月28日
幅広く「実学)探求
地域との連携21世紀も貫く
 北大のバンカラに比べると、樽商大生は紳士的だったというが、寮生が上半身裸でストームを踊るのは同じようだ=1942年
北大のバンカラに比べると、樽商大生は紳士的だったというが、寮生が上半身裸でストームを踊るのは同じようだ=1942年
 ほぼ全講座分の約90室あるゼミ室。学生たちはゼミの時間以外にも集まり交流を深めている
ほぼ全講座分の約90室あるゼミ室。学生たちはゼミの時間以外にも集まり交流を深めている
緑町にある学校直属の石鹸工場に行き…私は川崎昇と二人で作った金で石鹸の大箱を買い、荷車を借りてそれを公園通りの夜店の場所まで運んだ。…学校の石鹸は有名で、その品質のいいことは誰でも知っていた。石鹸はよく売れ、右隣や左隣の露店より、私たちの店の方が繁昌した。
一九二五年(大正十四年)に小樽高等商業学校(現小樽商大)を卒業した小説家伊藤正は、自伝的小説「若い詩人の肖像」の中で、「高商石鹸」について書いている。高商生の伊藤は同人誌の資金づくりのため、友人と夜店を出して高商石鹸を売ったらしい。
緑丘五十年史によると、小樽高商は二〇年、せっけん工場を建設。学生は材料の仕入れや製造、市場調査、労務管理、原価計算などを行い、生きた経済、企業経営を学んだ。
「現在、国公立大で商学部があるのは一橋大とうちだけ。ほかでは、商学は経済学部の一学科にすぎません」。樽商大の山本真樹夫教授はこう前置きし、「せっけん製造という理系の分野でも商学に取り込んで学ぶのがうちの強み」と説明する。今でも生物や化学の講座があり、生物に関する卒論を仕上げ、商学士として卒業する学生もいる。
山本教授は幼いころから小樽に住み、樽商大修士課程を修了。道外の大学に七年間勤め、戻ってきた。「私が子供のころは、両親に商大生のようになりなさいと言われたくらい、紳士的で、模範的な存在でした。今も、北大を落ちて来た学生は最初はコンプレックスを持ちますが、商大の伝統に触れるにつれ、誇りを持つようになっていきます」
山田家正学長も専門は生物だが、「理系と文系に学問領域を分けるのは、実学と考えられる商学では意味がありません」と断言する。「薬品会社に就職して営業に回され、文系だから化学が分からないというわけにはいきませんから」
卒業生は高商時代から約一万人。地方都市の単科大学ながら、経済界を中心に有能な人材を輩出し続ける原動力は、こうした柔軟な発想にもあるようだ。
真の国際化と地域との連携。山田学長はこの二点を挙げる。来夏にオタルで開かれる国連大学のグローバルセミナーで樽商大が幹事校を務めるのも、具体的な取り組みの一つ。地元企業約二十社が資金援助も名乗り出た。
こうした地域の協力は、一八九〇年代後半に高商新設の話が持ち上がった際、地元有力者の寄付で用地などを確保し、ライバルの函館を押しのけて誘致を実現した歴史と重なり合う。
〈メモ〉
小樽商大は1911年(明治44年)に小樽高商として開学。44年に小樽経済専門学校、49年に樽商大となった。緑丘五十年史によると、06年、政府が北海道に高等商業学校の新設を内定。当初は凾館が最有力だったが、政府は建築費37万円のうち、地元が20万円を負担する条件で小樽設置を決めた。20万円は現在の金に換算すると一億数千万円という。
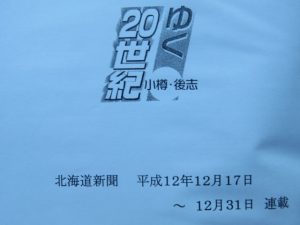 より
より
ゆく20世紀 小樽・後志3
 伊藤整と川崎昇が開いた露店は小樽公園側?
伊藤整と川崎昇が開いた露店は小樽公園側?

そば会席 小笠原
北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100
FAX:電話番号と同じ
E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp
営業時間:10:30~21:30
定休日:月曜日
