第十六話 昭和の世のうつろい
2017年02月20日
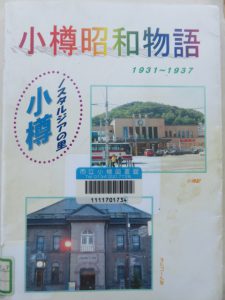 より
より
晩秋の冷たいみぞれが落ち始める季節になりますと、石狩川の河口をさかのぼる鮭達が網にかかります。大型トラックに柵をかけ、秋味の獲りたてを車一杯につみこんではこんできます。夜の暗い路上に裸電球の下に生きているかの様に並べられ、水をはった四斗樽の中で現れます。ベテランの老作業員達はマキリで腹をひきさき、メフンと白子と筋子に分類するのです。腹に荒塩をつめこみ、本州送りの準備をするのです。新鮮な筋子はショーユにつけて、一晩待遠しいがつけて食卓に並ぶのです。シシャモやニシンが大漁という電報が入ると、番頭さんは又肥料がとれたと嘆きますが、魚達が水揚げの時点での評価が何故そんなに違うのか価値は食卓評価の違いについて理解できないのです。自然に対する乱獲のたたりか、二度ともどらない昔の夢でございます。ニシン釜という遺産のみがさびはてた形骸として、浜の片隅に投げ捨てられてゐました。
昭和初期の恐慌は子供達にははっきりした記憶もありません。ナッパ服の作業衣を着た人々が生彩をかいた様に、運河ぶちのあちこちに力なく座ってゐました。その頃はルンペンという言葉がはやり暗い世相を感じさせてゐました。
又昭和の初期は商店街のお店も大きく入れ代り、様変わりしたことをうかがわせる一大恐慌の町の資料や地図も書き込んでみました。
その頃、良く父に連れられ数隻の商船に分乗した兵隊さんが満州に出征するのを見送りました。五色のテープとバンドに見送られ岸壁から船出をするのです。又各商店の青年も祝入営ののぼりをたて旭川師団に入隊するのです。
何故か人々の異様な動きのなかで、少年達は迷路の入口にも立った様な無情な世のうつろいを感じ始めたのではないでしょうか。
昭和三十年頃の雑誌と思いますが、小樽は昔からいくつかの城下町が散在している様な処だと評論されていました。崖や坂道が多いためか大きな石垣を積んだ城の様な家や、黒い板塀で囲まれた武家屋敷の様な家が富岡町や緑町方面に見かけたものあります。それらは海運商や政治家、漁業者、木材商とか北海道開発の先駆者達の邸宅であった様でした。
年末の御歳暮の季節になりますと親のお使いで毛色の美しい雉肉をお届けするのが冬休みのアルバイトの楽しみなのです。藤山汽船の邸は第二玄関から上がります。お取次ぎを頼み五分位待ちますと、衣ずれがして静々と和服の老婦人が畳敷きの大廊下から現れ、ごあいさつをうけるのです。一週間前から練習の私もごあいさつの口上を申し上げるのです。私にお使いの駄賃とその昔は珍しい玩具が何よりも嬉しいものです。名門藤山家は昔より行啓の節は皇族をお泊めするのですから礼儀、言語、動作は言うに及ばず、知識、素養については高いレベルにあったのです。
しかしながら、戦後の経済動乱のなかで、生き残れずすべてが水泡に帰してしまいました。こうして小樽の灯火(ともしび)が一つ消えたことは子供心にもさびしい出来事でありました。
小樽の景色で想い出にうかぶのは憂愁をふくんだ冬の日本海です。灰色の気虚空ときびしい深みのある暗い海との調和と一体感であります。白い波頭のくだける向こうに幻想的なすばらしい増毛の山脈や海原が水平線に続きます。車窓の景色は山はだをなめる様に右と左に変化するのです。それらを見ていると衝動的に画布に表現したい感動にかきたてられます。一方又積丹半島の岬には一刻ではありますが、暮れなずむ夕陽を浴び海と夕陽と黒い岬が石塔の様に屹立(きつりつ)しその自然の美しさに息をのむのです。多くの人々がこの実りや恵みの自然の豊かさを求めて、先人達が積丹の海の道をたどってきた歴史を振り返る時、この雄大な絶景はきっと今日も変わらず輝いてゐるものと思います。
 藤山邸のあった場所は
藤山邸のあった場所は
 『日本銀行の向かい三井ビルの隣、旧小樽貯金局(昭和27年落成 現在の小樽市立文学館・美術館)の場所でした。』
『日本銀行の向かい三井ビルの隣、旧小樽貯金局(昭和27年落成 現在の小樽市立文学館・美術館)の場所でした。』

そば会席 小笠原
北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100
FAX:電話番号と同じ
E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp
営業時間:10:30~21:30
定休日:月曜日
